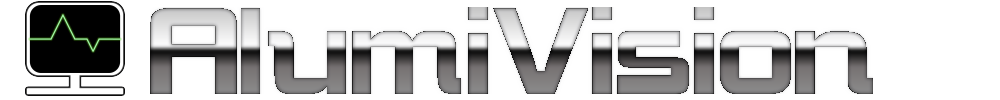M3-2024秋 入手物感想
これはなに?
このページは、2024/10/27のM3-2024秋に参加して、後に各種SNSで入手した物の感想を書いていたのを、体裁だけこのページ用にまとめて再掲したものです。
以下のセクションから文体が大きく変わりますが、文章そのものは元の感想文の最終バージョン(2024/11/17)から手を加えていません。
下記で繰り返す通り推敲不十分なところは多いですが、あらかじめご容赦ください。
また、文責はナイラーにありますが、これはサークル「アルミビジョン」の人間としてではなく、一リスナーとしての率直な感想を書いたものです。
少なくとも自らの利益のため他者を貶める目的で書いたのではないということ、ご理解頂いた上でご覧ください。
序文
この文章群は、私ナイラーが2024/10/27の秋M3で入手した楽曲/作品の感想を殴り書きしたものである。当然ながら私の主観や忖度が多分に入っていることを念頭にお読みいただきたい。
あわせて、文章の書き方の都合文中に出てくる人物や団体の名前には敬称はつけていない。 また他作業の合間に書き進めているものなので、文体統一や推敲など不十分になることが予想される。読む前にあらかじめこれらをご了承いただきたく思う。
7年ほど音系同人イベントに通ってきて、なぜ急にこんなことをやろうと思ったかというと、 コロナ禍を経て最大級の規模となったM3において、
「これ初めて来た人は何をどう探せばいいのかわかるのかな……」と老婆心ながら思ったものの、 回遊時に自分がやっていることを伝える有効な手段が思いつかずとりあえず入手物への全レスをやってみようと考えた、という経緯である。
私自身もかなり偏った音楽の趣味をしているのでディスクガイドの類として機能するかは微妙なところだが、 あなたが新たな世界を開く一助となれば幸いである。
凡例
以下、各作品は次のような凡例で記号を付けている。○通常の作品
□筆者とこのM3以前に明確な接点がある人の作品
◇筆者が参加している作品
各作品の感想
2024/10/29聴取分
○佐藤あんこ - 4から3へ
厳密にはこれは「M3で入手した」カウントに入れるべきではないのかもしれない。
というのもこれはリリース時にメカノに行く余裕がなくてDL版を買ったのを、今回KAOMOZIレーベルがM3に出展するというのを聞いて、 やはり物理で欲しくなって買ったものだからだ。なので他の作品と比べると明らかに視聴回数が多い(フェアじゃないかも)。
佐藤あんこは古くはニコニコ動画で80年代ニューウェーブのカバー動画を上げていた人物で、 P-MODEL/平沢進の非公式ギター譜「トロンプ・ロレイユ」を出した人物というとわかる人もいるかもしれない。
彼は近年ベネズエラの3拍子ポップ「ガイタ」を収集しており、その影響を受けて作られたのが今作である。 (なお今作はあくまでJ-ポップである。記憶してある限りで佐藤あんこ本人が今作を「ガイタそのもの」だと称したことはないはず)
先行でPVが公開された「BLOOM」もそうだが、 我々がパッと想像する3拍子のリズムとは異なる特徴的で魅力的なリズムをしている曲が多い。 というのも今作の収録曲は最初から3拍子であることを前提に作られたものではなく、 先に一度4拍子で全曲作り切り、そこから無理やり3拍子に押し込み直すという方法で作られている。 この押し込み直す処理方法が各曲で全然違い、小節の前に押し込まれていたり、後に押し込まれていたり、余剰分を別小節で消化したり……と、 手を変え品を変え再構築することで、ガイタとも違う新たな3拍子の世界が生み出されている。
○Higaki - ヤコブソン
京都の大所帯エレクトロスウィングバンドYummy Rusk & Caneleが活動休止するのに伴い、 中心人物のラッパーHigakiが始めたソロプロジェクトの2作目。
前作とは違い、(再録1曲を除いて)Higaki自身の作曲した曲はなく、 どーぱみん、SPYKEYという同人界隈でエレクトロスウィングを掘っているならまず聞いたことがあろうトラックメーカーの提供トラックでラップする形となっている。
各トラックメーカーのトラックももちろん極上なのだが、素晴らしくかつ恐ろしいのはもちろん、 これらのトラックと張り合いあまつさえ勝っていく、エレクトロスウィングラッパーHigakiの地力だろう。
○おはよウールズ - 徳育ファンク
柳井未奈人のten-bagger(旧作「ポンデワンダリング」収録)カバーをきっかけに知った2人組ユニット。
ギターポップに渋谷系風のラップが乗ったミクスチャーである。わかりづらければ「みんなノーマル」のころのゲス乙女を想像してくれればいい。
前作1曲目「So Far」を思い出す、やや重めのベースラインが流れてきて、しばらくしてボーカルがややだるそうに意味が通じそうで通じない歌詞を歌い始める。
ファンキーなギターと一緒にいろんなモノがいろんな遊びをして、いつの間に終わる……といった趣の曲だ。
○el ma riu - 機巧仕掛塔ラステアカノンのトルティーネ
物語音楽を作り続けているソロプロジェクトel ma riuの新作。人によってはVketの一部BGMの作曲担当として知っているかもしれない。
この作品は彼女の活動のかなり初期作のリメイク。 (ただし旧作との共通曲は1曲目と7曲目くらいで、ほぼ別物に近くなっている。「ルイと悪魔のノート」と「~SS」に近い関係か)
旧作が全部一人製作だったことのセルフオマージュか、今回も曲・絵・物語のすべてがel ma riu一人で製作されており、 年月を経たリメイクということでかなり気合の入ったグレードアップ・再構築がなされた新しい物語として楽しむことができる。
その大きな熱量の弊害か、このM3では2曲ほど欠けた途中版での頒布となってしまったが、 質の高い作品であることは間違いないので、歓迎の意思を持って完成版を待ちたい。
◇OX-project - LAST ЯESORT
(筆者参加曲 : Tr.03 Oracle Caravan - Search for Azcanta)
いつもお世話になっている、xyst率いるOX-projectの新作コンピ。
この作品は既存のTCGの「切札」たるカードをモチーフにした楽曲が集まっている。 集まった楽曲のモチーフになったカードは初出時期的にも収録タイトル的にも広範にわたりすぎているので、
個人的には初回はそれぞれモチーフになったカード自体を副読本として眺めながら聴くことをお勧めする。 各曲ともカード効果やイラストやフレーバーテキストがかなり高い精度で再現されていることがわかるはずだ。
ちなみに、物理版はガチの遊べるTCGとして頒布された。デッキを組むのは金銭面的に難しいが。
◎2024/10/30聴取分
□MiYAjY - MIDNIGHT ECHOES
日本でNEOY2Kをやらせたら右に出る者はいない男MiYAjY。
近頃大病で一時創作活動を休止していて、復帰一発目のEPである。 (ちなみに回遊のとき退院祝いとかを話しに行こうとしていたら完全に入れ違っていたらしい。この場を借りてお詫び申し上げる)
独特の「懐かしいダークさ」、NEOY2Kを言葉で表せばそういう感じなのだが、 彼の楽曲の場合それだけにとどまらず、今の音と懐かしい音を効果的に織り交ぜて、音で映像を上手く描き出しているように感じる。
「平成サイバー」は20年前のノスタルジーに消えたわけではなく「令和サイバー」として生き続けている、というか。
□MaNDAR∀ - Doux Moment
近年メキメキと頭角を現しているMaNDAR∀のミニアルバム。
普段のコンピ楽曲や前作「Bezel/CROWN」を聴いているとブレイクコアとかそのあたりのハードな音楽ばかり作っているようにも思えるが、 実は彼はかなりディープな渋谷系Jポップのコレクターでもあり、その趣向が反映されたのが今作だと思っている。
渋谷系の「イメージサンプリング」とDTMの一般的なサンプリングを同時にお出しすることで独特のおしゃれさとカワイさが描き出された5曲。 特に「Special
Party Set For Milk And Donuts!」はマジですごい。VEC5のあの意味わかんないサックスメロディサンプルなんでこんなにうまく使いこなせてるんだこの人。
○Scene From Gore Girls - 感情論 EP
ずっとエピック/シネマティックの作品を出してきたScene From Gore Girlsが歌モノロックのEPを出してきた!? しかも発売からM3まであまり時間のないSynthesizer
V AI 宮舞モカを使ってる!?!? ……と、そもそも告知の時点でかなり意表を突かれた。
実際に聴いてみると、もう宮舞モカを使いこなしているし、あの頃のロキノン系を想起するような良質なJ-ロックだし、 かといってところどころにScene
From Gore Girlsっぽい音使いは見られる、という不思議な作品だった。
○アタリメ - raspberry syrup
ずっと渋谷系一本で創作を続けているサークル、アタリメの新作。
今作はサブスク時代を意識したのか、一曲あたりの曲調がいつもと比べて短いような気がしたが、 実際に聴いてみると各曲アタリメらしいエッセンスは十分に詰まっていて、これが最適解というようにも感じる。
今回は各曲で作編曲作詞ボーカルの担当が全部違うので、ちょっとしたコンピアルバム的な要素もあって、 そのあたりを意識した聴き比べも面白いなと思った。
○terminus - ANTE EP
今回完全ノーマークで買った2作品のうちの1つ。恐ろしくソリッドにアーメンを刻んだドラムンベース。
terminusは旧マイルストーンのIP保持者のDJイベント「ARXIAL RENDEZVOUS」への出演経験があるそうで、 それを考えると確かにカラスやカラスBORの時のk.h.d.n.のテイストを感じないこともない。
基本的に全曲ひたすらアーメンを叩きつけてくる曲で、音階を感じるものはパッドくらいしかない。下手すると低音もたまに鳴るリリースの長い808キックくらいしかない。
ここまでメロディの薄い、ひたすら空間が広がっていくだけのドラムンベースは今日日なかなかレアなのではなかろうか。
自分でなんとなくわかった気になっていた「ドラムンベースがドラムンベースという名前たる理由」を再度考えるいいきっかけになった。
◎2024/10/31聴取分
○Pitohui Records - Robotronica
「トイトロニカ」というエレクトロニカのサブジャンルを基軸に、 可愛くて癒されるインストサウンドを追求し続けているPitohui Records。
近年はLo-Fi Hiphopにかなり傾倒した作品が多かった傾向だが、(まったく影響がないわけではないとはいえ)久々にトイトロニカメインの作品な気がする。
「ロボ」とはタイトルにあるもののどちらかというとブリキのおもちゃとかそういうアナログな自動人形がモチーフなようで、 そういう安めの金属缶的な小気味いい音がちりばめられている。 一方で可愛さ一辺倒というわけでもなく、時折挿入される不穏さは、 曲名と照らし合わせるとこのアルバムの世界観で何が起きているのか、断片的に読み取れるかもしれない。
◎2024/11/2聴取分
○フーリンキャットマーク - Heavenly Game
もはや説明不要なアキシブ系音楽サークル、フーリンキャットマーク。
世間的には諸事情で東方アレンジの印象が強いかと思われるが、 SOUND VOLTEX収録の「港町レディ」など、実際にはオリジナルも同じくらいの割合で作るサークルである。
しかもハイペースでハイクオリティ。だいたいM31シーズンに対して2~3枚の新作を用意する体力と創作力のお化けである。
今春から新ボーカルを迎え入れた新体制として再スタートする……ところだったのだが、 不幸な行き違いでその新ボーカルが1シーズンで脱退してしまい、元の体制に戻るといった出来事があった。 その経験を乗り越えて夏のライブアクト等を乗り切り出たのがこの作品である。
作曲担当の谷高マークの野球好きが反映されて、収録曲は全曲野球をテーマとしている。 過去に「恋するシャングリラ」で1曲入ってた「消えたスローカーブ」は高校野球テーマだったが、今回はむしろプロ野球を意識したような歌詞選びが目立つ。
(そこに再録で「えそらごとおままごと」を混ぜてるのは「group_inou - 9」的でなんか毒気があるというか)
それを支えるボーカルはド安定の正ボーカルの鳴沙ともはや準レギュラーのうぐ、それと過去作で「ふるしあんて」を絶唱したCapitanよりたまき。
プラス生楽器サポートとデザイナーで最強のナインが集まったアルバムに……
……今クレジット確認したら一人足りてなかったのでキャッチコピーじみたボケが崩壊した。そういうこともある。
○フーリンキャットマーク - 第三次仙人戦争
最近のフーリンキャットマークが東方オンリーイベントに合わせてよく出している印象のある、 原曲を1曲に絞ったEPシリーズの1作。
本作は全曲「デザイアドライブ」のアレンジ。
残念ながら筆者はそのあたりの東方原作をプレイしていないのでアレンジとしてどうかという評価をしようがないのだが、 各曲に共通するフレーズを拾うことで「ああ、いつも通りオシャレにぶっ壊してるな」ということは感じ取れた。
基本的にフーリンキャットマークの東方アレンジは歌詞に原作をあまり反映させないのと、 相当大胆に曲構成を変えてくる(実例を挙げると原曲のサビを前後分割して、片方をAメロ、残りをサビで使う)などするので、
余り原作に詳しくなくても独立した曲として聴けるのが個人的に嬉しいところ。
○Kashiwade works. - Luminous Code
Kashiwadeとは直接の面識はないのだが、今回氏のスペースで売り子をしていた人物とつながりがあったので購入させていただいたもの。
氏の持ち味は壮大なオーケストラ/エピックミュージックで、過去何かの偶然で「Conquest」を聴いた時に脳天を撃ち抜かれた覚えがある。
今作でもそのベースは変わらないが、そこに意図的に細く儚いピアノ曲や淡々と事実を語るようなボーカル曲が混ざることで、 作品の「物語」としての解像度と裾野がグッと上がっているような気がする。
○DIVERSE SYSTEM - AD:GARAGE
この文章を読んでいるような人にはあえての説明も不要な気もするが、 DIVERSE SYSTEMは当初音ゲーアレンジメインで、諸事情あってオリジナルコンピに転向した大手サークル。
また他のサークルの物理通販を一手に引き受けたりもするので、同人イベントには参加しないが同人音楽を追ってはいる……という層はそれで名前を見ているかもしれない。
そんなサークルがUKガラージのコンピを出す、それ自体は不思議ではない。 DIVERSE SYSTEMの最初の最初は2003~4年くらいと記憶しているので、中核人物は音ゲーを通してガラージ/2stepをいっぱい聴いているとは予想する。
ただ……本気度が違う。
AD:TECHNO5が出た時に速攻ブースに買いに行ってその時の売り子に同様の言葉を伝えた気がするのだが、 今作も「メンツが本気すぎて今日日商業でも出てこない」。
good-cool、平田祥一郎、Tomoki Hirataといった日本で2stepが流行った時の当事者、 KO3やRay_Ohといった同人から商業に行った若くエッジなクリエイター。
プラスリスナーとしての流行りの当事者である与作が選び出した公募曲。
そんな強力なクリエイターが集まった結果、再ブームの今どころかブーム当時でもありえなかったような、 最強のガラージアルバムが完成していた。
本当に怖いほどクオリティが高い。なにこれ。
◎2024/11/3聴取分
◇OX-project - ??UN=I:DENT!ℲIƎꓷ??
(筆者参加曲 : Tr.03 60kVの衝撃 - マクアフティル=アイスヴァインの漸近法則)
存在しない物コンピ、あるいは不明コンピ。 「この世界(筆者や読者諸兄の生きる世界のことである)にないもの」に説明をつけ、それを音で表現するというコンセプトのコンピアルバムである。
そんなお題を与えられていつものOX-project周辺の面々が盛り上がらないわけがなく、 各自普段つくらないジャンルを作るのは当然として、さらに奇怪な音や構成を詰め込んだ、
まさに鵺のごとき異形のコンピレーションとなった。
□Fenrir records - Weekend Cafe
とあるつながりで知り合ったLamb.の個人サークルFenrir records。
普段は他からボーカルを招聘して歌モノメインの作品を出しており、もともとは本M3でもボーカルアルバムを出す予定だったそうなのだが、 製作中にメイン歌唱を予定していたボーカルが諸々の不調に見舞われてしまい、急遽本作品が生まれたとのことだ。
タイトルやジャケットを見てわかる通りのカフェ/ラウンジでかかっていてほしいタイプのちょっとボッサな感じでまとめられている。
沙羽のボーカル/コーラスも意図的に主張しない程度に抑えられていて、 それこそ実際の飲食店などのBGMとして「いい意味で」サッと聞き流せる1枚になっている。
○ねこぜなおとこ - ぬりえ1号
長年ボカロPをやっているねこぜなおとこだが、一部界隈では「変な頒布方法」の先駆者と見られていて、 実際「紙飛行機」「豆本アルバム」などCDという形式にとらわれない楽曲頒布を行っている。
(筆者が今回のM3で出した「はんこコンピ」も元をたどれば氏へのリスペクトである、ということはあえて申し添えておくべきだろう)
そんな彼が今回の頒布方法として選んだのは「塗り絵」。 塗れと示されている部分を塗るとQRコードになって楽曲がダウンロードできるという仕組みだ。
このあたりの頒布形態で遊ぶ発想力では勝てる気がしない。
○リリィミズサキ - ステップはお静かに EP
元々は10/29聴取分のHigakiの前作「雷風がたり」でフィーチャリング参加していたのを覚えていたので買ったもの。
そちらでは気持ちスローテンポめな楽曲に合わせて細い歌声だったので個人名義でもそういうタイプの曲が多いのかなと思ったら、 むしろ正反対で、エレクトロスウィングのど真ん中みたいなトラックにパワフルな歌声を叩きつける気持ちのいいほどの楽曲が集まっていた。
曲が全体的に短い(ほぼ2分)なのが少々残念だったかもしれない。それはアルバムに期待するものなのかも、だが。
○JACK MATE - SABBAT II
同じく「雷風がたり」のフィーチャリング参加で名前を覚えていたので買ったもの。
JACK MATEは上記のリリィミズサキとエレクトロスウィングDJ/トラックメーカーの前線のユニットである。
前線のトラックは自らエレクトロスウィングで回してるからこそなのかの「遊び」が多く、 本作でもガラージリズムを基調にしたものなど、おそらく自分でDJ中の飛び道具として使うつもりなような曲がいくつかある。
型破りは型を理解していないとできない、とはよく言ったもので、ちゃんとエレクトロスウィングを理解しているが故の崩し方がとても心地いい。
○Casket - The Drowsy Sun
今回ノーマークで買った2作品のうち1つで、北欧系インストかつ頒布物デザインが良かったので買った。 (回遊してた時気づかなかったが、初期スマホ音ゲーの界隈では有名なEscarmewのサークルだったらしい……マジか、リサーチ不足だった)
楽曲は本当にガッチガチのアイリッシュで、(クラシックのほうの)ミニマルに近い繰り返し音楽である。 (「そういうジャンル」なのだ)
もちろん展開上ある程度形式が変わるところもあるが、努めて「ムラが出ないように」演奏しなければそれっぽくないのは、 逆に人らしいムラを求める筆者のようなDTMerにとっては一種のカルチャーショックかもしれない。
○空読無 白眼 - creature
今回筆者の隣のブースで参加していた空読無 白眼の1stCD。
彼はBMS作家で、BMSを出す時には必ず5鍵譜面を入れる……というか7鍵を入れないことすらある、 その上曲自体も近年の商業音ゲーと直結したテイストとはまるで違う、「もしplugoutシリーズが続いていたら絶対に参加してただろう」感じの作風をしている。 というかplugout5にいる。
この作品自体はBMS作者の1枚目としてはよくある「既存BMSをロング化したもの」ではあるのだが、 それを念頭に置いて聴いていても1曲目の1音目から頭をぶん殴られてしまう。
トライバルともエレクトロともつかない、しかし何か秩序を為そうとしている"ソレ"が、 我々リスナー側のナメた態度を粉砕してくる、そんな作品だ。
しかもそれが10曲分も勢いを落とさずに殴りかかってくる。 覚悟ができる人間には極めてお勧めの1枚だ。
◎2024/11/4聴取分
○棗いつき - ENIGMA
棗いつきは当初個人サークルで音声作品の製作・出演と歌唱活動をしており、現在一二三株式会社に所属しているボーカル。 彼女と親交の深いnayuta、藍月なくるとのコーラスユニット「La
priere」のメンバーとしても知られている。
筆者はElis Dogma以降の作品しか把握できてないのでもしかするとそれより以前を考慮すると話は変わってくるのかもしれないが、 会社に所属していなかった時期と所属して以降の「作品の一貫性」は評価すべき点だと思う。 もちろん一二三所属前後の作品で製作スタッフを眺めるとほとんど違う名前が並んでこそいるのだが、 所属前の「CodeQ」や「Happy Enforcer」あたりと所属後の「UNDERTAKER」や今作を連続して聴いたときに感じる違和感はほとんどないはずだ。
元々1枚の作品で濃いストーリーを表現するのを持ち味としていて、時には特典としてショートストーリーを書き下ろすこともあるほどだ。 既にアーカイブ削除済みのYouTubeライブでの発言だったかと思うが、元々ラノベ書きを目指していた時期もあったらしいので、その経験が生きているのであろう。
本作品自体は「魔術」「怪異」といったものを軸にしたストーリーが組まれている。
筆者としては先にインスト版6曲を聴いた後に戻って通常版を「歌詞を見ずに」聴いて、その上で歌詞カードを読んでほしい。 怪異に力あるモノと力なきモノが相対した時どうなるか、苦戦してそうなインストが実は勝ち確演出の曲だったりすることもあるので、
そういう強者と弱者の視点の差が体感できると思う。
また聴き終わった後は、物理版であれば上記の通りショートストーリーがついているので合わせて読むと世界観の理解が深まるだろう。
□月面終末観測所 - COMPOSE 1900
昔存在した音楽共有サービスMQubeで名を馳せたFullMoonが、 現在作品発表の拠点としているのが個人サークル「月面終末観測所」である。
サークルでは彼女個人の作品や手がけたUTAU音源の配布のほかに大規模コンピを手掛けることもあり、 今回のM3で2作品出たコンピレーションのうちの1つが今作である。
(もう片方のコンピレーションに絡めて触れるのが遅くなりそうなので先にここで触れておくと、 恥ずかしながらこのコンピレーションに提出して不採用になった楽曲をリサイクルしたのが今M3での筆者の新作「sacrifice
EP」だ)
コンピタイトルに見覚えがありそうでない読者も多いだろう。 このコンピは例の犬の表紙でおなじみ某英単語帳をモチーフにしたコンピで、各曲の曲名も実際にその英単語帳に掲載されているものになっている。
当然ながら曲自体もその英単語を表すような音像をしている。 (これはFullMoonの弟に「これで1個くらい英単語覚えろ」、という意図とのことだ)
また、ブックレットにはそれらの単語の例文も乗っている。 著作権の関係上オリジナルの例文となっているが、これがまた面白くて読みごたえがあるので、 是非とも購入して読んでみてほしい。
○Nekoribo - Ribbon×Cat×Box!!
近年スマホ音ゲー界隈で急激に名を轟かせているNekoriboの1stアルバム。
彼は実は相当作風が広く、打ち込みでオーケストラができるほどの手練れではあるのだが、 アルバムとして方向性がブレすぎるのを危惧してか、今作では基本的に音ゲーコアをメインに絞って、時折味変として別ジャンルを混ぜる形で収録されている。
新鋭故のフレッシュさに独特なキュートさを帯びた音ゲーコアが来たかと思うと、 次にはどこかのゲームでいつかボス張ってそうだなあと感じる丁寧かつ邪悪に音数を増やした楽曲が来る。 とある一次創作のキャラをイメージしたボーカル曲や頭を冷やすためのピアノ曲…… 次々と手を変え品を変えた曲が飛び出してくる、まるでびっくり箱のような作品だ。
◎2024/11/6聴取分
○ConCreate - ConCreate Club Mix
急に個人情報バラシをやるのだが、筆者は兵庫県立大学の姫路工学キャンパスに通っていた。
そのころの学部3回か4回生(たぶん4回生だったと思う)の、新歓時期に初めて名前を見たのが、 当該キャンパスのDTMサークル「ConCreate」だった。
といっても、筆者はすでに研究室配属されてたころだったので、すさまじく気になってはいたのだが特に関わりなく大学生活を終えた。
(ちなみに気になっていた理由の一つが独特なブレイクコアを多数制作していたサイコドラゴン先生が在籍していたからだ。 直接な関わりではないがStepMania界隈でも一時期存在感を示していたので名前を覚えていた)
Twitterアカウントをフォローする程度には追いかけていたし、M3に行きだしてからもカタログで名前を見てはいたので存続しているのは知っていた。 (サークルスペースに行ったことはなかったが) が、2022年か23年からカタログに名前がなくなったので「もしかして消滅した?」と思っていた。 それが今回久しぶりにサークル参加しているということに気づき、一度行ってみることにした。
スペースでお話を伺った限り、残念ながら「学生サークルとしてのConCreate」は消滅してしまったようだ。 後継者が入会してくれず、現役学生の所属者がいなくなってしまったらしい。
今回の参加もほとんど歴代のOB会に近かったらしい。
こういう形で存続していればいいっちゃいいのかもしれないが、周りを新陳代謝が成功した学生サークルに囲まれている状況ではやるせなさはあったと察する。
まあある意味学生時代にコンタクトを取ろうとしなかった自分も同罪なのだが……
長々と自分語りを絡めて書いてしまったが、そういうわけでConCreateに所属していたOBたちによるクラブミュージック系のコンピだ。
「OB会」という状況を意図してなのか違うのか、実際収録曲は学生サークルとして活動していた2015~2020年くらいのビッグルーム感があるジャンルで占められている。
あの時代を作曲とともに生きた人間であるなら、このコンピを聴いて何か感じるものはあると思う。
Tr.04が白眉。
□Dem Nota Veloce - Dance Extra Music
Dem Nota Veloceは個人VTuberでDTMerでゲーム製作者。 氏はStepManiaを大幅に改造した自作音ゲーを製作しており、その縁で1月の音けっとで少しお話させていただいた。 ちなみに今回の出展はその音ゲーの所謂ロケテストも兼ねていたようだ。
音けっとのときは東方アレンジのスピードコアで、今回はオリジナルのスピードコアだ。 上記の音ゲーの実質的なサントラでもある。
ゲーム向けに調整してある(ついでにBPM変えたりシーケンス止めたりできるシステムもある)のでかなり実験的な要素も多いが、 ジャンル特有の疾走感は感じられるはずだ。
○INF HARDCORE Records - インフィニティ・オトゲイズム! -Junk Crown-
INF HARDCORE RecordsはHiyとHARXDistortionが中心になって運営されているハードコアメインの音楽サークルである。
昔セブンスコードという音ゲーアプリで二氏の名前を見て覚えていたのと、 Hiyにはゲームセンター支援団体iwate EVOLVEDの活動で(きわめて間接的だが)お世話になっているのもあって今回スペースを訪問した。
このCDは2年ほど前に同サークルからリリースされた「インフィニティ・オトゲイズム!」の続編で、 やはり今作も架空の音ゲーを想定した作りになっている。(おそらく想定がbeatmaniaIIDX16~20なのも同様)
ラストにロングバージョンがおまけでついてるのもわかっている作りだなあと思う。
強いて言えば筆者は(相当曲りなりにではあるものの)収録曲のバランス取りとか頻繁にやってる人間なので、 「ちょっと低速足りてなくない?」と思いはしたものの、これは本来のサークルのカラー上譲れないところか。
◎2024/11/8聴取分
○Halv - 魔法世界とインターリュード
J-COREや各種音ゲーへの曲提供でおなじみ、Halvのミニアルバム。 ……11曲入りでミニアルバム?(これは本人もセルフツッコミをしている)
こういう表記なのは、この作品が音楽的にもストーリー的にも前に出したフルアルバムと後に出るフルアルバムのインタールードにあたるからだそう。
楽曲については安心と信頼、いつものHalvクオリティ。 だがそのクオリティを維持したまま、本作品のタイトルが示すようなファンタジー要素を特盛している。
Tr.03やTr.08あたりはいつものHalv楽曲のパブリックイメージが頭にあると、方向性の違いに驚くのではないだろうか。
強いて言えば全曲ほぼ音ゲー尺なのがもったいない気もするが、これも「ミニ」アルバムだからだろうか。
□Hmt2 - Traumerai
数々のボーカリストやVTuberとのコラボ楽曲を製作し続けているHmt2のアルバム。
氏とは旧名義時代にとある人物の企画を介して接点があったのだが、いつの間にか高いところまで上り詰めていて、以降新譜が出たらあいさつがてら買いに行くくらいの細い繋がりが続いている。
デカくなりおって……(後方彼氏面)
この作品はインスト楽曲と歌モノ楽曲がだいたい半々の割合で入っている。
インストは昔から変わらず、しかし確実に現代的なアップデートがなされている、EDMをHmt2流に再解釈したダンスミュージック。 打って変わって歌モノではオシャレ系なサウンドに変わる(この二面性こそが氏の持ち味だ)。
かといってそれら二種類が乖離しているわけではなく作品内でしっかり筋が通って繋がっているのは流石というほかない。
◎2024/11/10聴取分
◇月面終末観測所 - White Hawk
(筆者参加曲 : Disk4 Tr.07 ナイラー - 風待草)
今年の元日に発生してしまった、能登半島地震とそれに伴う災害。 その救助および復興支援のため、自らも防災士としての現地派遣経験を持つFullMoonが春M3にて開いたチャリティコンピが「Bright
Notes」、 本作はその第二弾にあたる。
楽曲面としては「企画上極端にふさわしいもの」でなければ全てを受け入れているので、 方向性こそさすがにバラけているが(全部で80曲超えているので)、高クオリティかつ大量の楽曲を一度に手に入れることができる。 Disc1におそらくAD:GARAGE公募の落選供養と思われる楽曲が固まって収録されており、個人的にはそのあたりの楽曲が嬉しかった。 あと、単純にコスパが高い(=楽曲数が多い)と、リスナーとしてはその分お得感もあるので、企画としてはまさにWin-Winか。
なお、実際の売り上げについては前作同様、どうしても必要な経費分(製作費と募金の振込手数料)を除いて全額が日本赤十字社に振り込まれている。 これはコンピ参加者の一人としてここで証言しておこう。
□Sunajiro - Starry Orbit
ネット上で先に知り合っていたSunajiroのアルバム。
宇宙がテーマとのことだが、基本的には氏の持ち味である突き抜けるハードコアを軸にしている。 そこに氏の別の軸である歌モノJ-POPを挟んで一貫性を持たせている形だ。
一部宇宙の広大さ・恐怖を表すようなインタールードを挟んで宇宙がまるごとやってくる、というわけだ。
ちなみにSunajiro本人によるセルフライナーもあるので、興味があって楽典を理解できているなら視聴後に読むといいだろう。 (恥ずかしながら筆者はそのあたり何も知らずに作曲をやってるので一部理解ができなかったところもあるのだが)、
各曲の音価やコード進行まで踏み込んで仕掛けられた、このアルバムの世界観の「真相」がわかる。
□hexatropica. - エルゴノーツ
Yuugaoを中心としたサークルhexatropica.による、「ブックレットのイラストストーリーのサウンドトラック」という性格のあるコンセプトアルバム。
海中列車に乗った少女の経験した出来事を音に起こしたようになっている。
「海中」ということを反映してか、全体的にストリングスや淡いシンセ音をメインとした、優しいサウンドでまとめられている。
もしブックレットを一緒に見ない場合でも、エンディングっぽい性格のTr.12~13は除いて、 Tr.01から水深がだんだん深くなっていき、Tr.05~06で運行する最深部に到達し、Tr.11に向かってまた水深が浅くなっていく……という流れは耳だけでも感じてもらえると思う。
□hexatropica. - 摩天楼
同じくhexatropica.より、再びイラストストーリーのサウンドトラックのようなコンセプトアルバム。 こちらは「街と『逆さまに』そびえている摩天楼」にまつわるストーリーが展開されている。
「深きへ向かい」「ファンタジックな」前作エルゴノーツと対照的に「高きへ向かい」「近代的で」あるからか、 大幅なサウンドの転換が行われていて、エレクトロなクラブミュージック要素が強い曲でアルバムの大半が占められている。
前作とほぼ差のないメンバーでここまで音を変えられるということに、作風の広さがうかがえる。
そして―――逆さまな摩天楼に昇り切った、ということは、高天に放り出されたことに等しいということで。
◎2024/11/12聴取分
○音ゲー同好会 - ハピコア流星群
初頒布当時に周りの知り合いがマストだと言っていたので、今回下記の~Ⅱリリースに合わせて一緒に買ったもの。
音ゲー同好会はその名の通り、音ゲーが好きすぎてボルテをはじめとした近年の音ゲー公募に頻繁に顔を出している面々が集まったサークル。 Bemani
Pro Leagueでプレイヤー側としての参加経験があるseatrusが一番わかりやすいが、 他の面々も一定以上のプレイヤースキルを持っており、決して名前だけの集団ではない。
さて、今作品は(初頒布の当時には)その時の音ゲー界隈で最盛期ほどの存在感がなくなっていた、 所謂P*Lightスタイルの音ゲーハピコアを集めたコンピアルバムである。
前述したとおり各メンバーが近年の音ゲーでよく曲を提供しており、ほぼ全員が近代的な音ゲーハピコアを作れる (というか、一人その「近代的な音ゲーハピコア」を定義したサウンドを出した人が混ざっている)のに、 あえてボルテ勃興期っぽい音に寄せたのは、おそらく遊ぶ側としてのリスペクトなのだろう。
○音ゲー同好会 - ハピコア流星群Ⅱ
今回のM3でリリースされた、上記の続編。
引き続き2013~2016年頃の「あの頃の音ゲーハピコア」が収録されている。 サウンド傾向こそ同じだがメロディなどに前作や他者作品などと似た雰囲気すら出さないのは、 まるで「我々音ゲーマーはこのジャンルを掘りつくしてないぞ」と宣言しているようだ。
◎2024/11/13聴取分
◇EXABIT RECORDS - Rapid Music Writing 4
(筆者参加曲: Disc2 Tr.11 Assault - RECT)
2年前に始まったこのRTAコンピもとうとう4作目だが、サークル主のteraoの実社会事情のため今回が一旦の最終回となってしまった。 そういう理由もあって今回初めてCD媒体で頒布された。
4作目とデスマーチに引っかけて「死」がテーマとなっており、音で表現された多種多様な死を聴くことができる。
なんなら3回見たら死ぬ絵ならぬ3分聴いたら死ぬ曲みたいな、不安を全力であおりに来る曲もある。こわいね。
◎2024/11/14聴取分
○Ark of Phantasm - 種族×職業コンピ
某Misskeyインスタンス経由でご挨拶頂いたウィナのコンピレーション。 (私信 : 別の打ち上げの予定があってカオス飲み断っちゃって申し訳ないです)
ファンタジー感のあるコンピを複数企画しているらしく、参加者単位では何人か知っている作曲者もいて、 「異種が生きる異世界の日常」がよく描かれていると思う。
◎2024/11/16聴取分
◇OX-project - Limit Breaker XX
(筆者参加曲 : Disc2 Tr.11 ナイラー feat. GUMI - BRILLIANCE♡AZURE / Disc4 Tr.08 ナイラー
feat. GUMI - ポート・グリント)
いつものM3の風物詩、会場焼きコンピもついに20作目の大台に突入した。 今回はその20回という節目を記念して、「過去の会場焼きのうち任意の2作品」をモチーフにした楽曲が集まった。
筆者が持っているのは9作目以降なのでそれ以前のネタがあまりわからなかったりするが、 それでも「あーこれはこの回のネタだな」とわかる部分があるので、
今までの全作品を追えてる強者にはとくにおすすめの逸品だ。
◎番外編
○破損CD研究 - OMOCHA
筆者も含めて、「実物を出す意味」を模索しているサークルは結構ある印象だが、 その中でも特に尖っているなと感じたのがこの作品だ。
CDそのものに焼かれているのはアンビエント系のサウンドなのだが、盤面を物理的に破壊することで、 各個体ごとに全く違う音が鳴るようにしてある。
残念ながら今手元に潰していいCDドライブがないので拝聴できていないのだが、 こういう前衛芸術みたいな実験がなされるのが同人音楽のいいところだと思う。
○KAOMOZI - KAOMOZINE
この感想を書き始めようと思った直接の理由が、戦利品の一つであるこの雑誌だ。
基本的にはKAOMOZIレーベルのメンバーによる自作についての書き物なのだが、 一コーナーとしてレーベルメンバーによるディスクガイドが記載されており、
「こういう『なに聴いたらわからないときの道しるべ』みたいなのやりたいな」と触発されてこのテキストを書いたのだ。