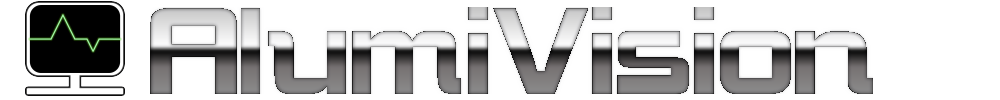音けっと第8楽章 入手物感想
これはなに?
このページは、2025/6/1の音けっと第8楽章に参加して、後に各種SNSで入手した物の感想を書いていたのを、体裁だけこのページ用にまとめて再掲したものです。
以下のセクションから文体が大きく変わりますが、文章そのものは元の感想文の最終バージョン(2025/6/1)から手を加えていません。
下記で繰り返す通り推敲不十分なところは多いですが、あらかじめご容赦ください。
また、文責はナイラーにありますが、これはサークル「アルミビジョン」の人間としてではなく、一リスナーとしての率直な感想を書いたものです。
少なくとも自らの利益のため他者を貶める目的で書いたのではないということ、ご理解頂いた上でご覧ください。
序文
この文章群は、私ナイラーが2025/6/1の音けっと第8楽章で入手した楽曲/作品の感想を殴り書きしたものである。当然ながら私の主観や忖度が多分に入っていることを念頭にお読みいただきたい。
あわせて、文章の書き方の都合文中に出てくる人物や団体の名前には敬称はつけていない。
また他作業の合間に書き進めているものなので、文体統一や推敲など不十分になることが予想される。読む前にあらかじめこれらをご了承いただきたく思う。
春M3に引き続き、今回も入手物を聴いた感想を書いていこうと思う。
イベント自体を知らない人や興味がある人向けに説明を入れておくと、「音けっと」というのは大阪は難波で2018年から開催されている音系同人イベントで、
途中コロナ禍による中断をはさみながらも、基本6月/12月の年2回開催されている。
規模感としてはだいたい100スペース台前半くらいで、今年の春M3と今回の音けっとの実績値でいうと10~11分の1くらいだと思ってもらえばわかりやすいか。
その分「サークルと一般参加者、およびサークル同士のコミュニケーションを濃密にする」ことに重点が置かれた施策がとられており、
イベント最中に希望サークルがスピーチして会場中にアピールすることや、コロナ禍明けの再開以降のネットラジオとの連携など、
「知ってもらう場」としてはうってつけなイベントだと考えている。
また、M3ではなかなか見られない方々がいるのも地方イベントならではである。多分交通費とか云々。
参加サークルの大雑把な傾向(ジャンルであるとか使うものであるとか)もM3とはかなり変わってきており、そこを感じるのも一つの楽しみ方かと思う。
筆者が把握している限り、現状では音系同人イベントは東京のM3と大阪の音けっとしか存在しておらず、
首都圏と近畿圏以外ではある程度財力がないとイベントに参加しづらい状況ではあるので、各地方都市圏単位で同趣旨のイベントが立ち上がってくれないかなというのが、
筆者の願うところである。
私自身もかなり偏った音楽の趣味をしているのでディスクガイドの類として機能するかは微妙なところだが、 あなたが新たな世界を開く一助となれば幸いである。
凡例
以下、各作品は次のような凡例で記号を付けている。○通常の作品
□筆者とこのM3以前に明確な接点がある人の作品
◇筆者が参加している作品
各作品の感想
◎2025/6/3聴取分
○真島こころ - 水のフレア
元々流麗なピアノ曲を作ることで有名な真島こころ氏だが、昨年バズったフリーホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」で製作したフリーBGMが引用されたことで、
知名度がさらに上がった印象がある。そんな氏のオリジナルアルバム。 曲は全てピアノインストだが、ブックレットには各曲「詩」が書き下ろされている。
それぞれ水をテーマとした叙景詩であるが、この詩をベースに曲ができたのか、それともできた曲からの着想でこの詩が書かれたのか、 いずれにせよ合わせて視聴することで感じる物は変わってくるだろう。
○白瀬抄一 - 浮遊と下降
ジャケットを貫く赤線を見ればわかる人はわかるであろう、平沢進オマージュの作品。 一昨年まで活動していた馬骨擬装綱や、同人シーンには出てこない方だが山下憶良などと同趣旨といえば通じるだろうか。
具体的にはBLUE LIMBO~点呼する惑星の「弦(=ストリングスセクション)」を強調し始める直前のサウンドのテイストを感じた。 一方で平沢の、というか日本ニューウェーブに特徴的な「意図した錯誤的な歌詞」はほぼ見られない、
というか意図的に若干雰囲気を感じる程度に抑えてあって、それゆえに氏の自身の言葉という感じ方が強くある。
○Yufica - YUME ARCHIVES+
J-core~Future系ジャンルを集めた作品。 歌声合成によるボーカルが多用されているのだが、ボイスバンクのチョイスが筆者が見たことないものが多く、
曲間でのバンク被りもないので一種の博覧会のようになっている。 肉声ボーカルの曲もいくつか混じっているが通しで聴いても違和感がなく、作編曲力の強さを感じる。
○ETE - 白盤
これは会場のスピーチイベントで流れた曲が非常に気になって購入した物。 ポップで音数の多いオシャレファンクといった感じ。ループが多いのも洋楽的と取れるかもしれない。
こういう偶然の出会いがあるのが音けっとの醍醐味という感じだ。
○地獄のべくちゃん - 胡乱と九龍
M3の時にサークルスペースからポスターが見えて「アレ欲しいな……」と思って、いざ回遊タイミングで行ったら売り切れてたという悲しみがあったのだが、
今回音けっとに出展していたのでこちらで購入した。 「サイバーパンクとしてのエセ中華」がテーマのようで(九龍って言ってるし)、なんとなくオリエンタルなメロディに朦朧とした歌詞が絡む、
ただならない作品に感じた。
◎2025/6/4聴取分
○GOM-TAO - DanceHistory
「ハンズアップ」というトランスのサブジャンル一本で勝負しているサークルjealouSPECTの一枚。
こう……1ジャンルだけで勝負できる方、本当にそのジャンルにほれ込んで打ち込んでる感じがあって、 いろんなジャンルを浅くつまみ食いした作り方している筆者にとってはかなりうらやましい部分がある。
実際今回初めて知ったサークルではあるが、聴く前から安心感と信頼感があったし、実際聴いてもそれが揺るぐことはなかった。
○GOM-TAO - Don't stop speech
同じくjealouSPECTからハンズアップCD。 テンション高めのメロディが次々と出てきて非常に良い。 今回の2枚は両方ともEPだったが、アルバムか何かでもっとどっしりと腰を据えて長時間聴いてみたいと思った。おしながきを見逃しただけかもしれない。
□DJ XROAD - Miracle
クラブミュージックと立体音響の融合を進めているDJ XROADの新作。 前半3曲はハードスタイル系のトラック、後半3曲がそれらを立体音響化したものになる。
一般的な左右の空間処理とは違った、前後上下にまで振られた新鮮な音空間が楽しめるのは今記憶しているところこの人の作品だけだと思う。
○SBFR - Re:SSDX
とあるゲーム作品の二次創作メドレーを中心としたCD。あえて何のかは触れない。 しかし、筆者のようなニコニコ動画をRC1あたりから利用している層にとっては懐かしく今でも熱くなる物であることは間違いない。
◎2025/6/5聴取分
○CHRONOS RECORD - Condornika
ケーナ演奏者beckmanの作品。タイトルを見て察せる方も多いと思うが、「コンドルは飛んで行く」という有名な民謡に近い、
管楽器を中心に据えたインスト作品集である。 レトロゲーム機のRPGとかが好きな人間(筆者のような)だと、これを聴いていると「ああ、あのゲームは本当はこういう編曲がしたかったんだろうな」と思うような、
耳なじみが良くてそれでいて広々とした空間を感じる曲が集められている。
◎2025/6/6聴取分
○ArgentuM - たそがれの行く先
ArgentuMのトランスアルバム。
モチーフとしてアルバム内で時刻が設定されており、Tr.1は夜10時ごろから始まり、そこから夜明けに向けて後続のトラックが続いている。 「トランス」で「夜中」だが過度に瞑想的というわけではなく、むしろ常に一定以上ハイテンションである。
それがむしろ夜の闇に追い立てられているような想像を掻き立てるというか。何かを意図して徹夜するような日に聴く曲として格別なものだと思う。
○Azell - Aquatica
フリーゲーム「アクアリウムは踊らない」のBGM作者真島こころのブースにあったアレンジアルバム2枚のうちの片方で、 こちらはAzellによるアレンジ。
原曲は一部を除き概ねピアノ独奏に近い曲が多かったが、そのイメージを保ちつつも少々のパーカッションとシンセパッドでアンビエント風にアレンジしてあり、
違う方向に「水」を感じられるだろう。
□monoLR - Mono-Techno LP 3
記念すべき音けっと第1楽章から自身のテクノを貫き通しているUDLRの別名義がmonoLRである。
"mono"とある通り、この名義では意図的にモノラル化された、「狭い空間」でのテクノを追求している。 その分表現の幅も狭くなってしまうのだが、そこはさすが、巧みな音作りと磨き続けてきたソリッドなリズム構築でうまくまとめきっている。
◎2025/6/7聴取分
□Nekoribo & TAKIO - ULTIMAWEAPON
音ゲー系コンポーザーのNekoriboとTAKIO2人のスプリットアルバム。
特にTAKIOについてはちょうど1週間前ほどに太鼓の達人に楽曲が入曲していたので見覚えがある方もいるのではないだろうか。 春M3でNekoriboのアルバム2枚を買いにブースに行ったときに存在自体は把握していたがその時は予算不足で諦めたもの。
「音ゲー」という共通項こそある二人だが、それ以外の部分についてはクラシカルなバックグラウンドのあるNekoriboと生粋のポップ屋のTAKIOでかなり方向性が違い、
本人たちもそれを把握したうえで入念にすり合わせたのか、お互いの長所を生かしつつも決してその長所が「浮いて」しまうことはない作品となっている。
○真島こころ - アクアリウムの少女たち
昨日のAquaticaに引き続き、「アクアリウムは踊らない」のアレンジアルバムで、こちらは原曲作曲者の真島こころによるセルフアレンジ。
素材曲のゲーム内での使われ方を踏まえたリアレンジと、各キャラのライトモチーフとして書き下ろされた完全新曲で構成されている。 ゲーム内楽曲と同様全曲一貫してピアノ曲で、実際のゲームで使われてはいないがサウンドトラックに近いのかもしれない。
□monoLR - MonoTLP4
若干タイトル法則が変わっているが、昨日の「Mono-Techno LP 3」の続編で、やはり「狭い」音像にこだわったテクノが収録されている。
狭さをさらに推し進めて、ある細線上の「流れ」を巧みに制御しているような印象を覚えた。 それは各トラック単位の曲内でのリズム構築もそうだし、今回は作品全体の収録順もかなり効果的な緩急をつけたのだと認識している。
またモノラルトラックにもかかわらずかなりはっきりと音の位置(ここでは音量と周波数)が住み分けられているのも見事だった。
◎その他
けしのみ工房 - CureSynth mini
今回たぶん唯一のハードウェアで出展していたサークルで、所謂「ハードMIDI音源」。10年くらい前にあった「NSX-1シールド」と似たようなものと思ってもらえばわかりやすいか。
(ほぼ)音源専用チップだったそれとは違い、これはサークル主が作ったMIDI再生プログラムがArduino上で動いている。決してリッチな音ではなく命令もGM1範囲しか受け付けないが、近年一部で盛り上がったPure MIDIムーブメントとの親和性であるとか、独自に実装されたサンプリング機能であるとか、
作曲道具としてのポテンシャル自体はかなりありそうに感じた。